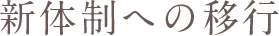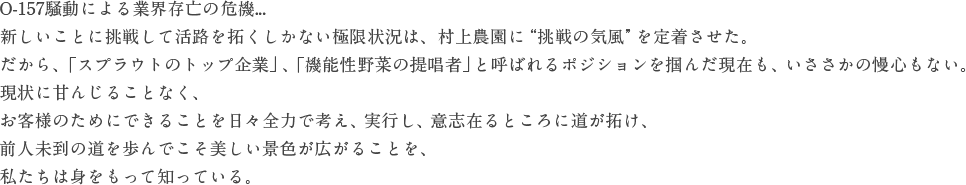しかし、そんな専門家の“常識”も、洪水のごとく押し寄せるマスコミ報道の前には何の意味もなかった。
出荷量はみるみるうちに前年比30%まで落ち、社員は「テレビで見たけど、本当に大丈夫?」と殺到する電話への対応に追われていた。市場やスーパーマーケットなどへの事情説明にも飛び回らねばならなかった。
最も動揺したのは新入社員だったかもしれない。大学院でイネ科の植物を専攻した研究開発部の加茂慎太郎(当時)もその1人。
事件後、同期や先輩が次々と辞めていくのを見ていた。
「どうするんだお前。入ったばっかりだし、辞めるんだったら早い方がいいぞ」。酒の席でそう語る先輩もいた。故郷の九州にいる両親からも、「長男なんだし、早く辞めてこっちに帰って来い」という電話が頻繁にかかってきていた。それでも加茂は踏みとどまった。「会社がどん底になるって、そうそう見る機会はないでしょう(笑)ダメならダメで、いい経験になるかもしれないという開き直りもありました」。だが、経営者にとっては辞めて済む話ではなかった。村上秋人は、堺で騒動が起きたあと、消費者の質問にQ&A形式で応えるチラシを作って商品に入れさせた。
そうした努力が徐々に実を結んだのか、激減した出荷量も年末には前年比40%、翌年3月末には50%まで回復していた。夏には元に戻ると期待していた矢先の97年4月4日、愛知県蒲郡市と 横浜市の一般家庭で食中毒が発生。冷蔵庫に残っていた調理済みのかいわれ大根からO-157が検出(産地では未検出)され、出荷量が再び18%と激減した。「もはやこれまでか...」と、村上秋人は倒産も覚悟した。苦労して来たさまざまな出来事が頭をよぎった。
のちに“O-157騒動”と呼ばれ、日本全国を揺るがすことになるわりには、静かな幕開けだった。もっとも、大きな被害を出した1996年以前に、この食中毒菌についてどれだけの人が正しく知っていただろうか。
病原性大腸菌O-157が最初に騒ぎとなったのは、1982年の米国。日本では84年に初の感染が報告され、90年代に入ると毎年のように集団感染が起こるようになっていた。しかし、村上農園の社員や家族たちにとって、まだ対岸の火事でしかなかった。
いや、村上農園に限ったことではない。日本全国のかいわれ大根生産者にとって、これから先の大騒動は、まさに青天の霹靂だった。
事態が一変したのは96年7月13日のことである。
大阪府堺市で児童255人が食中毒症状を訴え、翌14日には患者が2000超にまで拡大(※最終的な累計患者数は9523人)、入院患者は791人を数えた。
集団食中毒自体は各地で起きていたが、かいわれ大根生産者にとって、以後“堺”は特別な響きを持つようになる。当初から感染源が給食だと見られたことで、厚生省(現・厚生労働省)は文部省(現・文部科学省)などと連携して調査に乗り出した。
使われた食材が総点検され、犯人探しが始まった。
そして、疑われたのがかいわれ大根。
生産業者にとってはまさに青天の霹靂とも言える出来事だった。「かいわれ が感染源とは...、本当じゃろうか」。
新聞やテレビのニュースで事態の推移を見守っていた、村上農園社長(当時)、村上秋人はつぶやいた。
野菜がそのような菌で汚染される話など、聞いたことがなかったからだ。植物の細胞は、細胞壁という丈夫で厚い壁と、細胞膜と呼ばれる柔軟な膜の壁によって守られている。この2つの壁の隙間を通れるのは、水と無機養分のような小さな分子だけ。隙間の200倍も大 きい大腸菌が、植物の体内に摂り込まれるはずがなかった。


1927年10月、村上秋人は広島市で生まれた。
地元の旧制農学校を卒業した村上秋人は広島県経済連に就職するが、お役所的な風土が性に合わず上司ともめてばかりいた。秋人が特にケンカ早かったというわけではない。戦後それまでの価値観がことごとく否定された結果、若者達は年長者に対しても持論を堂々と述 べる術を身につけるようになっていた。秋人もそんな若者達の1人であった。経済連は農協の仕事の中でも主として農産物の販売を受け持っていたが、終戦後の混乱期にあって、何でもありの状態だった。あるとき秋人は倒産した針工場の債権者会議に参加する。いろいろと口を挟んでいると、ひょんないきさつから社長を引き受けることになった。会社勤めにもの足りなさを感じていた彼にとっては渡りに船。「苦労は多いかも知れんけど、やってみたかった」。
こうして、村上秋人は経済連を辞めて企業経営に乗り出した。
倒産した針工場は従業員が100人ほどの規模だった。材料は鐵鋼メーカーから仕入れ、13の工程を経て縫い針や刺し針に加工し、インドや中南米などに輸出する。朝鮮戦争による特需景気で商品は飛ぶように売れた。だが、“特需”というものは所詮は長くは続かないと読んだ秋人は余裕のあるうちに次の手を打った。
バイクのディーラーだった。
当時バイクが大流行し、国産だけで100以上のメーカーが乱立していた。いち早くそこに目を付け、参入を果たしたのだ。

だが、競合の多さや業界としての限界を感じるようになる。
とくに手形取引の難しさを痛感し、現金取引が可能な事業はないかと模索した。すると、ヒントは一番身近なところから見つかる。ほかでもない母親 が、刺し身のつまに使われる紅タデを栽培していたのだ。
考えてみれば、旧制農学校出身で地元の経済連にも勤めながら、退職したあとの秋人は農業に関する知識や経験を生かそうとはしなかった。それどころか、農業とは距離を置こうとさえしていた。しかし、紅タデならば栽培方法も心得ていた。母親の細腕と小さな紅タデが、長年にわたって母子の生計を支えていたのだから。

さっそく全国のかいわれ大根生産現場を視察した。
当時、かいわれ大根の栽培方法には二つあった。砂耕栽培と水耕栽培だ。主流の砂耕栽培では散水の際に葉の裏に砂がついてしまう。水耕栽培はその心配はないが、日持ちがしなかった。この両方の問題を解決する栽培方法が確立できれば事業化は十分可能だ。テーマはこうして絞られ、秋人は研究に没頭した。
翌78年、特殊なマットを使った水耕栽培に成功。従来の土耕栽培よりも低コストで大量生産ができる体制を整えた。需要の喚起も必要だ。高級野菜として添え物に使われる程度だったかいわれ大根を、もっと身近な野菜として広く使ってもらいたい。そんなある日、秋人は寿司屋でネタの代わりにかいわれ大根を巻く「かいわれ巻き」を考案。馴染みの寿司屋に頼んで市場で実演してもらった。「かいわれ巻き」のさっぱりした口当たりが多くのお客さんに支持され、かいわれ大根はクチコミであっという間に全国に浸透した。
その後農場の規模を広げ、順調に売り上げを伸ばすが、新規参入業者も増え続け、80年代半ばには熾烈な価格競争に突入する。これに対しては、製造業で培った徹底した合理化とコスト削減がモノを言った。収穫から箱詰めまで自動化を図り、徹底したコストの削減を行った。さらに、品質向上のための市場シェアNo.1を不動のものとした。事業開始から約20年。
経営努力が実を結び、順風満帆と思えた矢先、秋人を不幸が襲う。
兄弟や父親をたてつづけに失い、自らも闘病や被ばくを経験してきた戦前・戦中。あの混乱の中を飛び回って、さまざまな事業を手がけた戦後。そんな時代と比較すれば、紅タデの栽培を始めてからの日々は、村上秋人にとって人生で初めてともいえる穏やかな毎日だった。しかし、工業製品とは異なる点も多く、発見の日々でもあった。たとえば市場価格だ。
工業製品ならばある程度予測もできるが、農産物の場合、今日100円で売れたものが明日は1000円、数日後には10円に暴落することもある。世の中の景気や需要動向に大きく左右されるのだ。しかし見方を変えると、タイミングを見計らって出荷すると高く売れるということだ。現金取引という点に惹かれて始めた事業だが、秋人はいつしか農産物を扱う面白さに目覚めていた。
そんな日々が再び破られる。
1976年に「200カイリ問題」が発生したのである。翌年には経済水域が設定され、漁業の衰退が声高に叫ばれた。「刺身需要と連動する紅タデにも影響するのではないか」。秋人は紅タデだけに頼ることに危機感を抱き、品目の転換を考え始めた。そこで目をつけたのが、かいわれ大根である。当時のかいわれ大根は少量ずつ木箱に入れられ、料亭などで吸い物の彩りや添え物などに使われる高級食材だった。秋人は製造業の経営で培ったノウハウを生かして、かいわれ大根を大量に安定的に生産できないだろうかと考えたのである。

当時“高級品”だったかいわれは、木箱に詰めて出荷していた


再び1996年へ話を戻そう。
堺で集団食中毒の起きたこの年、村上農園の出荷量は例年の30%にまでダウンしていた。社員の半数を半年間一時帰休させ、7つの農場のうち4つを操業休止することで対応した。この年、24億円を見込んだ年商は18億4800万円にとどまった。それでも、冬の季節を迎えて食中毒騒動が収まるにつれ、市場も落ち着きを取り戻してきた。
しかし、翌97年、横浜と愛知でO-157による食中毒が発生。
再びマスコミで大々的に取り上げられ、消費者のかいわれ大根離れは決定的となった。会社の前途を悲観した若手社員は次々と辞めていった。この年、村上農園は売上高10億円を割り込み、同業者は次々と倒産した。
会社存亡の危機を救ったのが、新商品「豆苗」だった。
「試験栽培は94年から始めていましたが、農場内には本格的に生産するのに必要なスペースがなかった。それに何か新しいことに取り組まなくてはいけな いといった危機感もなかったんです。ところが、事件のおかげというべきか、かいわれ大根を作らなくなったことで空いたスペースを使って豆苗が作れるようになった。以後次々と新商品を出しますが、会社にとっては一つの転機だったのかもしれません」現社長・村上清貴はこう振り返る。豆苗が、加熱調理をして食べる野菜であったことも幸いした。サラダとして生食するかいわれ大根に疑惑が持たれた結果、アピールしやすくなった側面もある。
生産現場や研究開発部のスタッフも含め全社員が店頭に立ち、豆苗の試食販売を続けた。研究開発部の新入社員だった加茂慎太郎も白衣をエプロンに替えてスーパーマーケットの店頭に立った一人だ。「会社の危機に見切りをつけて辞めていく先輩もいましたが、会社の危機に大切な販促を任されて使命感に燃えていました。もっとも最初のうちは研究室とは雰囲気の異なるスーパーマーケットの現場でまったく勝手がわからず、試食宣伝販売をやっている他社の女性に一から教えてもらいました」と振り返る。西日本営業所次長の吉川和秀は、栄養価が高くおいしい豆苗の魅力を伝えると共に、具体的な調理方法やメニューの提案が不可欠だと考え、精力的に飲食店を回った。トップシェアのかいわれ大根に依存していた事件以前の村上農園では例のないことだった。
再建の陣頭指揮を執ったのが現社長で当時常務であった村上清貴だ。「豆苗にとどまらず様々な情報を集めて精力的に新商品の開発に取り組みました。うちで栽培できないものは、委託生産農家を開拓して自社ブランドとしての販売にこぎ着けました。この時開発した数多くの商品の中には失敗したものもありましたが、新商品をどんどん出すことで取引先からもこれまでと違う目でみられるようになりました。」と村上は語る。
こうして、全社一丸となった豆苗シフトと新商品開発が功を奏し、操業中止していた4つの農場も徐々に再開できるまでになった。O-157騒動はたしかに禍(わざわい)ではあったが、この経験を通じて学んだことが次のステージで開花する。そしてその頃、やがて村上農園を飛躍的に成長させることになる「小さな芽」が海の向こうの米国で産声上げていた。


1997年、米国ジョンズ・ホプキンス大学(米国・メリーランド州ボルチモア)教授のポール・タラ レー博士が、ブロッコリーのスプラウト(新芽)に高濃度に含まれるスルフォラファンという物質に、「腫瘍の形成を抑制する効果がある」と学会で発表した。米国立がん研究所により、がん予防効果の高い食品約40種類が発表され、消費者の間で食品による疾病予防の意識が高まっていた時期でもあり、このニュースは三大ネットワークやCNNなどで頻繁に取り上げられ、スプラウトブームが起きる。
オレゴン州にある村上農園の関連会社ISSI社からこの情報を聞きつけた村上秋人社長(当時)はすぐに動いた。
「ブロッコリーも大根と同じアブラナ科野菜。スプラウトの形状も似ている。予防医学の研究報告があるのもいい。とりあえず米国に行ってみよう。」
「秋人はすぐピンとくるものがあったようですね。実は私は最初はそんなに期待していなかったんです(笑)。“腫瘍の形成抑制効果がある”と言われている食材は他にもありますし、眉唾なものも少なくない。しかし、調査を重ねるうち、確かな科学的裏付けのある野菜であることがわかり、これだと思いました」と村上清貴(現・社長)。

歓談する村上秋人
早速、日本での特許ライセンスを得るため、同大学の研究室を訪問するが、発芽野菜に長い歴史を持っているとはいえ、海外の著名な研究機関との交渉など初めての経験だ。最初のうちは門前払いの日々が続く。日本からは既に複数の大手企業が博士にオファーを行っていることもわかった。しかし二人はあきらめず、博士のもとに足しげく通った。「交渉は厳しいものでした。しかし、日本市場で成功させるには、博士の協力は絶対に欠かせませんから、気後れせず懐に飛び込むしかありません。博士の場合、もともとブロッコリーを研究されていたわけじゃなく、予防研究をする過程でブロッコリースプラウトが出て来た。だから、奥が深い。科学者としての観点から生産者に課すハードルが非常に高いんです。」(村上清貴 現・社長)
1999年10月、幾度も渡米し粘り強く交渉を続けていた二人は、博士の自宅に招かれる。博士から告げられた内容は、オファーを受けた日本企業をつぶさに調査した結果、最終的に村上農園をパートナーとして選んだということだった。決め手は村上農園の発芽野菜栽培に関するノウハウと日本においてかいわれ大根のシェアがトップであること。博士はさらに、「野菜を通じて人々の健康に役立ちたいという村上の熱意に共感したのだ」と語ってくれた。そして翌年7月、国際特許を持つ同大学から権利を委託されたBPP社 (Brassica Protection Products)と日本国内におけるライセンス契約を正式に締結。有用成分スルフォラファンを高濃度に含むブロッコリースプラウトを国内で独占的に生産販売する権利を得た。「発芽野菜を通じて人々の健康に役立つ」というプライドが、O-157の騒動によって揺らぎかけていた。そんな中で、医学研究において全米トップにランクされる権威ある大学の信頼を得ることができたことは村上農園にとって大きなチャンスであり、企業として次のステージへの確かな道標ともいえるものだった。
「何となく体によさそうな野菜」ではなく「明確な目的のために摂る野菜」へ。
つまり、「機能性」に期待して野菜を買うという全く新しい消費パターンを創出するために、村上農園が最初にこだわったのはネーミングだ。形状で言えば「新芽野菜」や「かいわれ」などと呼ばれていたジャンルだが、 明確に差別化するインパクトのある新しい名称が欲しい。そこで、当時まだ一般的でなかった英語のsproutから“スプラウト”と命名。その響きの新鮮さはさっそく市場の注目を集めた。また、かいわれ大根の半分ほどの小ぶりなパッケージが売り場で埋もれてしまわないように、ブロッコリースプラウトに加え、色や味、用途の異なる「クレス」「マスタード」「レッドキャベツ」の三種類のスプラウトを加えて4種の「スプラウトシリーズ」として発売した。
健康情報番組が人気を博し始めたタイミングだった。
村上農園は、メディアに向けたシンポジウムを開催したり、趣向を凝らした楽しいホームページを農業分野ではいち早く立ち上げたりと、斬新なPR手法で積極的に情報を提供した。スプラウトは多くのマスコミに取り上げられ、生産が追いつかないほどの一大ブームを巻き起こした。スーパーマーケットの野菜売場にはスプラウトのコーナーが新設され、市場に“スプラウト”というカテゴリーを確立することができた。しかし、この「スプラウトシリーズ」の成功は、次に投入する本命商品をスムーズに展開するための、いうなれば地ならしだった。

(大井川生産センター)
「ブロッコリー スーパースプラウト」。
これが、最新鋭の植物工場を新設し、商品化の準備を進めていた‘秘蔵っ子’の商品名だ。米国ジョンズ・ホプキンス大学のポール・タラレー博士が、腫瘍の形成抑制に効果がある有用成分スルフォラファンを発見したことは前述したが、その後の研究で、スルフォラファンはブロッコリーの特定の品種発芽3日目のサイズの新芽に特に多く含まれることが明らかになった。その研究に基づいた特定品種の種子を用い、米国からの栽培指導を受け、専用栽培装置で育んだ最高濃度の有効成分を含む最強のスプラウト、なのである。生野菜でありながら成分の含有量を自社研究室においてはもちろん、米国の提携検査機関でダブルチェックし、成熟したブロッコリーの20倍以上のスルフォラファンを安定的に含む、まさに“スーパー”を冠するのに相応しいスプラウトだ。
“野菜を機能性で選ぶ”という新しい提案は健康志向ブームに載って広く受け入れられ、「ブロッコリー スーパースプラウト」は一躍大ヒット商品となる。加工食品などと比べると極端に新商品が少ない青果マーケットに、新商品どころか“機能性野菜”というまったく新しい商品カテゴリーを創り上げた。会社倒産の危機から逃れるため、全社員が必至に新しいことに挑戦し続けた村上農園は、気がつくと「青果業界の仕掛け人」と呼ばれるようになっていた。


広島大学との共同研究により、本来植物には含まれないビタミンB12を豊富に含む「マルチビタミンB12かいわれ」を開発し、発売開始。
スルフォラファンを高濃度に含む「ブロッコリー スーパースプラウト」に次ぐ、有用成分に注目した野菜の第2弾として村上農園の柱の1つとなっている。

家族数の減少や単身世帯増加による少量ニーズに応える「ブロッコリー スーパースプラウト」ミニカップ (内容量20g)を発売。コンビニなどにも販路を広げる。

村上秋人が会長に就任し、新社長には1960年生まれの村上清貴が就任した。「C.C.C=Challenge(挑戦)、 Change(変化)、Chance(機会)」すなわち、「挑戦することで自分や周囲に変化をもたらし、チャンスを掴もう!」を合言葉に、若いリーダーの元でさまざまな経営刷新が行われている。



生食野菜生産施設として国内初となる食品安全マネジメント規格「ISO22000」の認証を取得。有害微生物検査を全拠点・全品目・365日実施、金属検出機の全生産センター導入、トレーサビリティを確立するため の全製品ロット番号記載など、業界最高レベルの安全工場活動を展開していることが高く評価された。